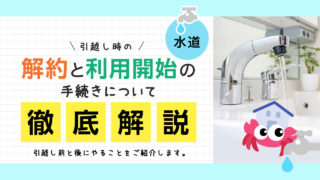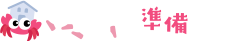水道料金は地域によって大きく異なり、全国水道代の格差は最大8倍あるといわれています。
8倍は極端ですが、2倍になる可能性は考えられるため、水道代が月5,000円の人は毎月1万円支払うことになるかもしれません。
引越ししてから、水道代の高さに気がついても遅いですので、今回は水道料金が高くなる仕組みと、引越し時のポイントについて解説します。
水道料金の計算の仕組み
水道を取り扱っているのは、各地域に存在する水道局のみであり、独占的に事業を行っています。
そのため業界内のシェア争いは存在せず、水道料金の価格競争が起こることもありません。
水道料金の計算方法
水道料金の計算方法は、以下の通りです。
水道料金=基本料金+従量料金
基本料金
基本料金は水道を使用するために支払う料金です。
水の使用量の大小で基本料金は変わりませんが、メーターの大きさ(口径)により支払う金額が決まります。
口径は、家に繋がれている水道管の太さをいい、水道管が太いほど一度にたくさんの水を送り込めます。
ただ口径が大きいと、基本料金は高くなる自治体もありますので注意しましょう。
(口径の大きさに関係なく、基本料金が同じ水道局もあります)
従量料金
従量料金は、水の使用量に応じて支払う金額です。
月に使用する水の量が多くなるほど、1㎥あたりの料金は上がり、従量料金の単価は地域によってかなり違います。
水道代は上下水道料金を合算する
上水道と下水道では、料金に差があります。
上水道は飲み水として使える水を供給する設備で、下水道は雨水やトイレ・洗濯などの生活用水を処理する設備です。
下水道は、汚水を下水処理場でキレイにしてから放水するため、処理費用分だけ上水道の料金よりも割高です。
基本料金・従量料金は地域ごとに異なる
水道料金の計算方法は全国共通ですが、設定されている基本料金と従量料金は、地域ごとに異なります。
たとえば千葉市は口径の大きさで基本料金が変わり、大阪市は口径の大きさに関係なく基本料金は一律です。
また同じ中心都市であっても、従量料金の単価はまったく異なります。
千葉と大阪の水道基本料金
| 口径 | 千葉市 | 大阪市 |
| 13㎜ | 418円 | 935円 |
| 20㎜ | 979円 | 935円 |
| 25㎜ | 1,749円 | 935円 |
| 40㎜ | 6,985円 | 935円 |
| 50㎜ | 15,840円 | 935円 |
2020年7月末時点
千葉と大阪の上水道の従量料金
| 口径(㎥) | 千葉市(1㎥) | 大阪市(1㎥) |
| 1~10 | 62.7円 | 11円 |
| 11~20 | 165円 | 106.7円 |
| 21~30㎜ | 268.00円 | 136.4円 |
| 31~40㎜ | 268.00円 | 184円 |
| 41~50㎜ | 444.40円 | 184円 |
| 51~100㎜ | 444.40円 | 253円 |
2020年7月末時点
1か月33㎥の水道を利用した場合(口径20㎜)
千葉市
- 基本料金 979円
- 従量料金 5,766円
- 合計6,745円
大阪市
- 基本料金 935円
- 従量料金 3,095円
- 合計4,030円
1か月で使用する水道量によって変わりますが、33㎥の水道量の場合、千葉市の方が大阪市より1.67倍も水道料金は高いです。
また同じライフラインでも、電気や都市ガスでは地域によって料金の差はありません。
したがって地域で料金が大きく違うのは、水道特有の問題であり、引越しする際の注意点です。
地域ごとに水道料金が異なる理由
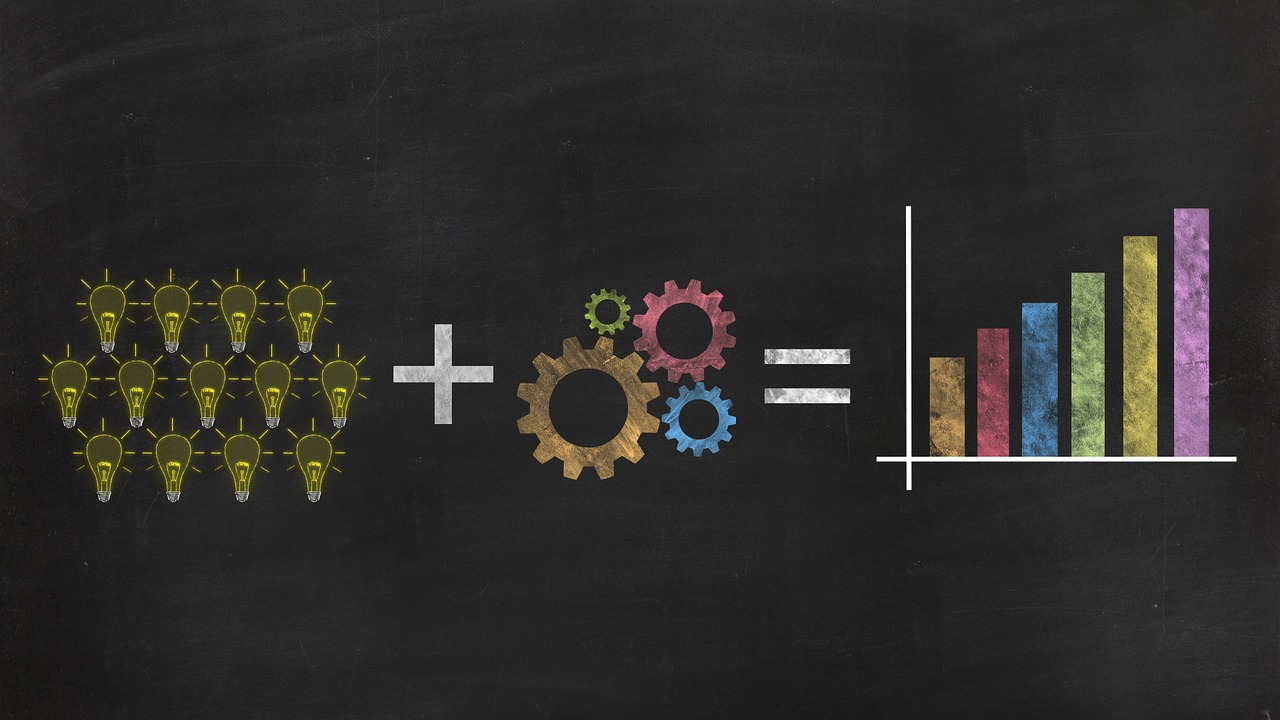
ライフラインの中で、水道料金だけが全国各地域によって料金に差が生まれるのは、3つの要素が関係します。
- 水を得るためのコスト
- 水を管理するためのコスト
- 水を使用するためのコスト
水を得るためのコスト
日本は海や川など、水に囲まれた国ですが、地域単位で考えると簡単に水を得るのが難しい場所も存在します。
また水源は、川以外にも地下水やダムなどあり、安定して水を得るための工事費用や設備投資は水道代でまかなわなければなりません。
したがってダムの建設費などを負担する金額が多い地域では、水道料金が高くなる傾向にあります。
水を管理するためのコスト
自宅で利用している水は、川やダムにある水をそのまま使っているわけではありません。
飲料水として利用できるまで、水をとして使用できるまでろ過処理などするため、処理コストが発生します。
また水道局で働いている人の人件費や、水道施設の費用、そして水道管の維持管理費も水道代でまかなっています。
維持管理費が高騰すれば、その分水道代の値上げをしなければなりません。
とくに近年では水道管の老朽化なども問題により、水道料金は今後上がると予想されます。
水を使用するためのコスト
水道局は、基本的に市区町村が管理しています。
農業が盛んな地域では農業用水として水を使用しますし、ベットタウンなら生活用水として水を使いますが、利用者が多ければその分水道管を延ばすことに。
また人口が少ない地域では、維持管理費用を負担できる人数(人口)が限られるため、水道料金に上乗せされる金額も多くなります。
たとえば経済破綻したことで有名になった、夕張市の水道料金は日本一高く、20㎥(口径13㎜)で6,870円にもなります。
6,870円は、全国的にも水道料金が高い千葉市ですら、33㎥(口径20㎜で6,745円)の水道量を利用できる金額です。
引越し先で水道料金が高くなってしまう原因

引越し先で水道料金が高くなる理由を3つご紹介します。
- 引越し先の水道料金自体が高い
- 親メーター方式で割高の料金が請求される
- 水漏れがないか確認する
引越し先の水道料金自体が高い
引越しで水道料金が高くなる一番の要因は、引越した地域の水道料金自体が高いことです。
先ほど紹介した千葉と大阪では、同じ量の水を使用しても、料金が1.67倍も違います。
また水道局は各市区町村が管理しているため、同じ都道府県でも水道料金は違うので注意しましょう。
親メーター方式で割高の料金が請求される
戸建て住宅の場合は、使用した分の水道料金を支払います。
しかしマンションなどの集合住宅では、親メーター方式を採用している場所もあります。
親メーター方式とは、マンション全体で使っている水の量を管理者や所有者が支払い、その後居住者が水道代を支払う仕組みです。
水道代は使った水の量が多いほど、1㎥あたりの単価が高くなります。
親メーター方式を適用した方が水道料金のコストを抑えられるケースもありますが、マンション全体で水の使用量が多いと、1㎥あたりの単価が上がるため、個別で契約した方が料金を抑えられることもあります。
なお親メーター方式から、戸別検針に切り替えられるかどうかは、引越し先の物件によってことなりますので、住居を決める際に不動産屋に確認してください。
水漏れがないか確認する
急に水道料金が高くなった場合には、水漏れをチェックしましょう。
たとえば蛇口をひねって水の勢いが弱くなっている場合には、どこかで水漏れが発生している可能性もあります。
(筆者は水漏れにより、月の水道料金が2倍になりました)
そのまま放置しても、水漏れは解消しません。
そのため水漏れを確認しましたら、すぐに修繕するなどの措置をしてください。
引越しで水道料金が高くなる理由のまとめ
引越し先で水道料金が高くなる理由のまとめです。
- 水道料金は地域によって異なる
- 料金格差は全国で最大8倍
- 水漏れにも気をつけること
水道は生活に必須であると同時に、引越し後料金が高いと気がついても、水道料金の単価を下げることは不可能です。
日々の節約で水道代を抑えることも可能ですが、単価が2倍になれば間違いなく固定費は増加します。
そのため引越し前に居住予定地の水道料金を確認し、そして引越しする部屋を決めましょう。